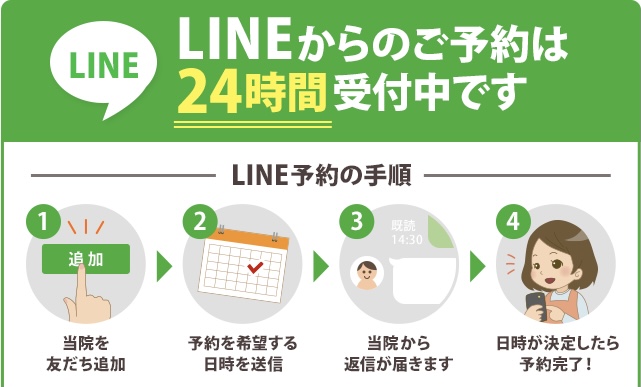
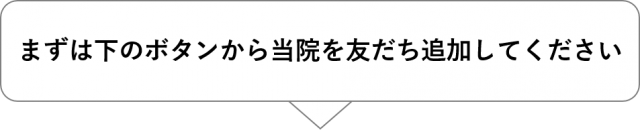
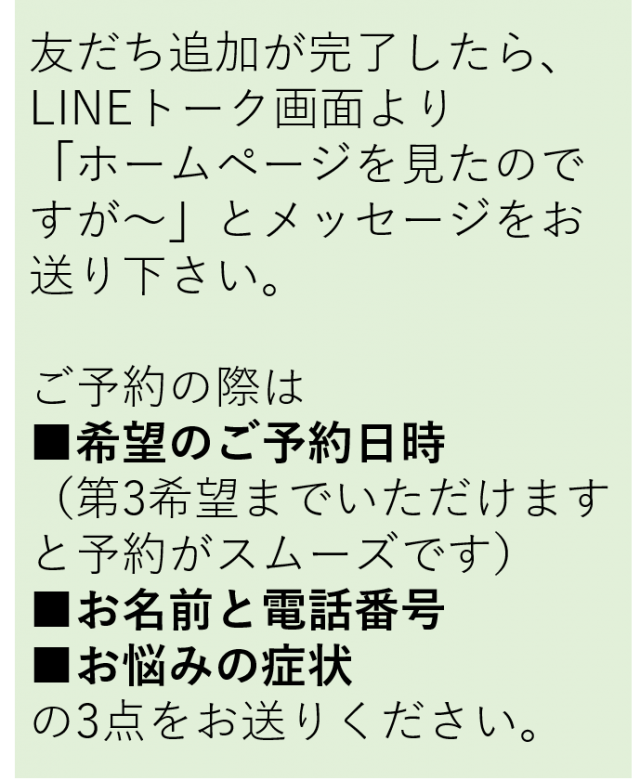
東京都品川区南大井、大森で【開業10年】たなか鍼灸院
長年の身体の不調でお悩みの方に向けて東洋医学で解説をしていきます
「お灸って熱くないの?」「なんのためにやるの?」 初めてお灸を受ける方の多くが、そんな疑問をお持ちになります。
お灸(きゅう)は、もぐさ(ヨモギの葉を乾燥・精製したもの)を燃やして、 皮膚の上または近くから温熱刺激を与える施術法です。 目的は「温める」だけでなく、身体の内側に働きかけて回復を促すことにあります。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 直接灸(点灸) | 小さくひねったもぐさを皮膚に直接置いて点火する方法。効果が高くなる一方、熱刺激は強めです。 |
| 間接灸 | もぐさと皮膚の間に生姜・にんにく・塩・紙台などを挟んで熱を和らげる方法。やけどのリスクを軽減します。 |
| 温灸・棒灸 | 棒状や器具入りのもぐさを使用し、皮膚から少し離して温める方法。ほんのり心地よい熱感が特徴です。 |
| 透熱灸 | もぐさを完全に燃やしきり、皮膚に熱が届くことでしっかりした温熱刺激を加える手法。 |
| 知熱灸 | 途中で火を消して皮膚表面がほんのり温かくなる程度で止める、やさしい刺激を重視した手法。 |
① 血流促進と代謝活性
温熱刺激により局所の毛細血管が拡張し、一時的に血流が増加します。 これにより酸素や栄養の供給が高まり、老廃物や発痛物質の代謝が促進されます。
② 自律神経への作用
お灸は副交感神経を優位にしやすく、 リラックス状態や胃腸の働きを促す神経反応が引き出されることがあります。
③ 免疫応答とホルモン分泌
温熱刺激によって皮膚からヒートショックプロテイン(HSP)の産生が誘導されるとされ、 細胞の修復、免疫応答の調整、ストレス防御に関与する可能性があります。
④ 白血球の増加や局所反応
温熱部位に白血球の集積がみられることがあり、局所の免疫防御を一時的に高める働きが示唆されています。
① 気血水の巡りと温補作用
東洋医学では「冷えは万病のもと」とされ、冷えにより気(エネルギー)・血(栄養)・水(体液)の流れが停滞すると考えます。 お灸はこの冷えに直接温熱で働きかける施術です。
② 五臓六腑への経絡刺激
お灸はツボ(経穴)を通して五臓(肝・心・脾・肺・腎)に間接的に働きかけます。
③ 虚寒(きょかん)タイプへの適応
お灸は虚証(エネルギー不足)と寒証(冷え)の状態に特に用いられます。
こうした体質に対し、温補(温め補う)施術として役立ちます。
お灸は、もぐさを燃焼させた温熱刺激で体にアプローチする伝統的な施術法です。
西洋医学的には血流促進、免疫や代謝に働きかけます。
東洋医学的には気血水の巡りを整え、五臓六腑のバランスを補う“温補”の方法として用いられます。
直接灸や間接灸、透熱灸や知熱灸などの多様な技法があり、冷え性・慢性疲労・胃腸の不調など幅広い不調に対応します。
体質に合わせてもぐさの種類やお灸の大きさなども変えて施術をおこないます。